茶の湯教養講座
(青山グリーンアカデミー)

Scroll
茶の湯への理解を深めるための教養講座をオンラインで開催しています。
パソコン・タブレット端末・スマートフォンのいずれかと、メールアドレスをお持ちであれば、どなたでも受講いただけます。
初めての方にも丁寧に対応させていただきますので、この機会にぜひ受講をご検討ください。
見逃し配信も行っています。日本各地、海外からも参加いただけます。
講座紹介 2025年10月開講の講座はこちら
《消息を読む》講座
「崩し字によって書かれる手紙を読む」
「崩し字によって書かれる手紙を読む」
《茶の湯文化学》講座
「日本各地の茶の湯」
「日本各地の茶の湯」
茶の湯が日本各地にどのように広がり、根付いてきたのかを紐解く講座です。
Read More《茶の湯茶書》講座
「稲垣休叟『松風雑話』を読む」
「稲垣休叟『松風雑話』を読む」
《茶の湯概論》講座
「茶の湯初心者を教える先生のための講座」
「茶の湯初心者を教える先生のための講座」
稽古を始めて間もない人を指導している教授者を主たる対象に、茶の湯に関わる様々な分野の基礎的な知識を確認し、日頃の指導の一助とする事を目指す講座です。
Read More《茶の湯の美》講座
「茶の湯とやきもの」
「茶の湯とやきもの」
代表的な日本のやきものについて陶芸家・研究者の方々を通じて理解を深める講座です。
Read More継続講座講師紹介
当講座では、茶道をはじめ広く日本文化に造詣が深い講師が指導にあたっています。
受講の流れ
従来、受講者ご自身で「事前登録」を行っていましたが、今期より毎月事務局で一括して登録を行う事になったため、視聴方法の流れが変わりました。
①お申込み
専用フォームよりお申込みください。

kouza@chado.or.jpから5日以内に
【受付完了】メールが届きます。

メールの内容を確認し、受講料をお振込み
ください。

②ライブ配信(生配信)の視聴方法
毎月、開講日の約1週間前にZoomから
【事前登録完了】メールが届きます。

【事前登録完了】または講座前日の【リマインダー】メールのリンクからZoomウェビナーに接続してご視聴ください。
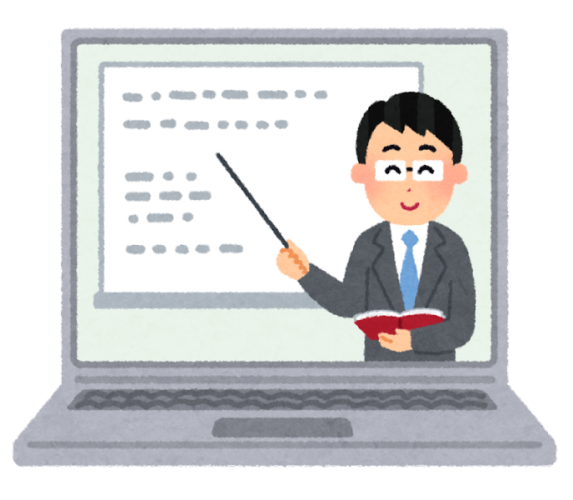
難しいところは事務局が
サポートします。
サポートします。
難しいところは事務局が
サポートします。

③オンデマンド配信(録画配信)の視聴方法
毎回、受講者全員にオンデマンド配信の視聴のご案内メールが届きます。

1週間以内であれば、何度でも視聴できます。

こんな時ぜひご活用ください。
☞講義の内容を復習したい
☞ライブ配信を見逃してしまった
お願い:配信内容の録画や受講を申し込まれた方の以外への公開は固く禁止いたします。
受講に必要なもの
①インターネット環境
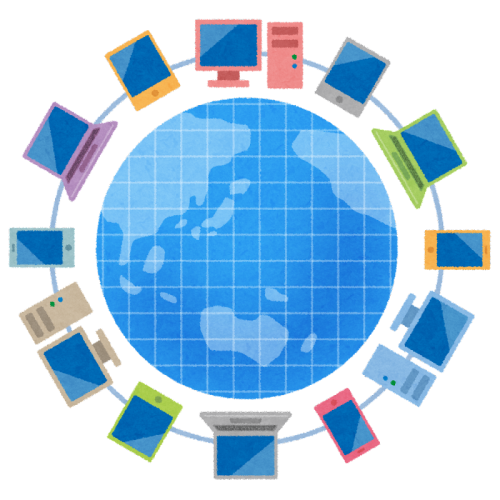
②パソコン・スマートフォン・タブレット
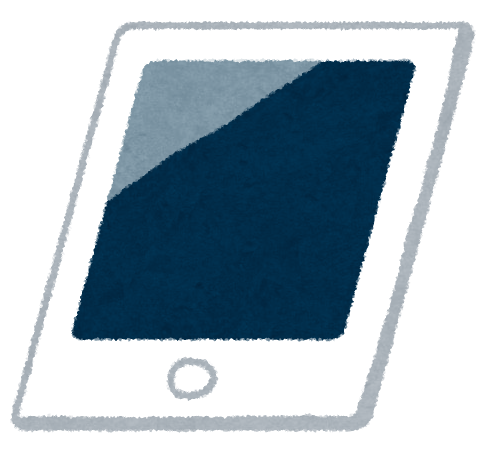
③メールアドレス
